社員をオフィスに戻すな! ──「ハイブリッドワークはこれからの企業のリトマス試験紙」 慶應義塾大学大学院・鶴教授インタビュー
コラム
コロナ禍で急速にテレワークの導入が進み、働き方は大きく変化しました。しかし、一部の企業では出社に戻そうとする動きや、ジョブ型雇用の必要性を説く声もあります。今回は、慶応義塾大学大学院 鶴光太郎教授に、二極化する日本企業のテレワーク事情や、なぜ企業は社員のWell-being向上に取り組むべきなのか、そして多様で柔軟な働き方を実現するためのポイントをお伺いしました。

二極化が進む日本のテレワーク事情。企業ジャッジの新たな「リトマス試験紙」は“働き方の柔軟性”
──アフターコロナの働き方についてお聞きするにあたり、まずはコロナ禍前後での日本企業の働き方の変化と現状を教えてください。
コロナ禍以前はテレワーク制度を利用しているのは大企業であっても1割前後でしたが、2020年4月に第一回目の緊急事態宣言が発令され、強制的にテレワークを進めたことで在宅勤務率は一気に跳ね上がりました。その後は、多少の振れ幅はあるものの、テレワークにうまく移行できたところはあまり比率が下がっておらず、うまくいかなかったところは以前のような働き方に戻すという二極化が進んでいる印象です。
取り組みの差が生まれているのは、企業が従業員に対するWell-being(編集注:ウェルビーイング。肉体的・精神的・社会的に良好な状態、幸福度、やりがいなどを含む概念)をどこまで配慮してきたかどうかに尽きます。コロナ禍以前から在宅勤務率を引き上げていたり、全員が自宅でも仕事できるような制度にしていたりなど、Well-beingに配慮してきた企業は必要な環境づくりに力を入れますが、従業員をコストとして見ている企業は、働き方が選択できる環境をつくることになるべくお金をかけたくないものです。
テレワークは、実は従業員が「職場から離れること」を許容する仕組みであり、長期休暇を奨励したり副業を認めたりといった取り組みと同様です。同じ時間に職場という同じ場所で働かないと駄目だという先入観が強い人は、テレワークのような取り組みには消極的だと言わざるを得ません。
──従業員に対する企業の考え方が、テレワークへの取り組み姿勢に大きく影響しているわけですね。
テレワークとは多様な働き方を象徴するものです。働き方改革とICT活用・デジタル化という二つの要素を組み合わせた交差点にあるものが、まさにテレワークです。コロナ禍以前は、テレワークは介護や子育てなど特別な事情のある方が利用する制度という雰囲気がありましたが、創造性や集中力を高める、つまりは生産性を高める手段としてテレワークがあるべきです。
実はエクセレントカンパニーと言われる企業は、コロナ禍以前からそのことを理解していました。従業員全員が制限なく働き方を選択できるべきで、柔軟に選択できることこそが、優れた企業かどうかのリトマス試験紙となるのです。そのような企業は、働き方改革やダイバーシティの推進施策を見ても、人材活用における先進的な取り組みを進めています。テレワークを行えているかどうかは、働く人にとって大切なWell-beingともつながっていると考えています。

オフィスに戻る動き、欧米の真似をしてはいけない
──テレワークがうまくいかない、となるとテレワークをやめて出社に戻す動きも出始めているようですが、このような動きをどう見ていらっしゃいますか?
従業員は通勤時間がなくなり、自分や家族との時間が増えてメリットを感じているなか、企業は出社させようとすることで理想の大きなギャップが生まれています。しかし、出社を中心とした働き方に戻そうとする動きについては日本に限った話ではなく、世界的にみられる動きでもあります。
ただし、日本と海外では大きな違いがあります。日本はメンバーシップ型雇用とよく言われる、新卒一括採用で同質的な人を採用し、同じ場所で長時間徹底的に情報を共有する。つまり、一心同体でベクトルを合わせていくことで“同じ釜の飯を食う”わけです。阿吽(あうん)の呼吸で上司のいうことを察して動くという、まさに社員が「情報システム」そのものです。そのためには、人力でコミュニケーションやコーディネーション(調整)を徹底的に行う必要があるため、会議が長く長時間労働になりやすい。ある意味では、日本企業の競争力はそのおかげで培われたとも言えるのですが。
──雇用形態の違いはもちろん、日本では社員が“情報システム”という位置づけにあると。
日本においては、サイボウズ製品が提供するような情報共有の仕組みは“人力”で行ってきたという年配の方も多く、情報共有をシステム化する必要性が理解できていないケースも多いです。
ここで大事なのは、ホワイトカラー系業務の生産性を高めるという視点です。インプットとアウトプットをデジタルによって見える化することで、これまでは当たり前だった仕事のプロセスにおける無駄が見えてくる。システムを導入することで単に情報共有や発信が容易になるだけでなく、仕事のやり方が変わってくるのです。
──逆に、欧米では情報共有を”人力”では行ってこなかったということでしょうか?
はい。欧米における組織・働き方の原点を、私は、「古典的ジョブ型」と呼んでいるのですが、徹底的に分業していくことで、従業員は限定された職務を上からの命令に従って進めていくというものです。むしろ、日本のように周りとの調整ごとやチームを組んで取り組む必要がないような組織や働き方がまずは志向・構築されたと理解すべきです。
しかし、1990年代に始まったICTによる情報通信革命により、これまで苦手であった部門間の情報共有・コーディネーションやチームワークがより容易になりました。それをしっかり取り入れることで、彼らは自分たちの働き方や企業組織を発展させてきたのです。日本企業で組織を支えてきたのは構成員である「人」であり、ICTを積極的に活用してきた欧米とは情報システムと呼ばれるものの捉え方が異なるのです。
つまり、情報共有の手段やその発展のプロセスが前提として異なるので、日本企業は欧米の動きをただ真似するだけではいけません。GAFAなど在宅勤務を禁止するような欧米企業の動きを見て、やっぱり在宅勤務は駄目なんだ、と日本企業が考えてしまうのは大きな勘違い。まず日本企業は、これまで取り組んでこなかった情報共有のシステム化を、これを機にはじめてみる必要があるのです。

テレワークには成果主義、ジョブ型雇用が必要だという誤解
──テレワークにおいては、仕事の様子が見えないため「成果主義」や「ジョブ型雇用」に移行する必要があるという考えも増えているようです。なぜこのような考えがでてきているのでしょうか?
テレワークにおける議論のなかで、ジョブ型雇用とともに成果主義への切り替えが必要だという意見はたしかに出ています。なぜそのような意見が少なからず見受けられるのかというと、それは、急にテレワークに切り替わったことで、上司は自分の部下が視界から見えなくなり、非常に不安感を抱いたからです。従業員にも、出社しているメンバーの方が評価されているのでは、という不信感が生まれ、在宅勤務に関する大きな課題となったのです。そこで、従来の雇用管理システムに問題があるのではないかということで、ジョブ型に注目が集まってきたという部分もありますが、これは大きな誤解なんです。
海外では、80年代にテレワークに関するさまざまな研究が行われ、当時はテレワークのしやすい仕事として、その人だけで完結する限られた業務で、成果が測りやすい仕事がいいといわれていました。それとジョブ型が連関している部分もあり、テレワークは成果で判断できるような仕事でないと評価は難しいのでは、という先入観に囚われて、テレワーク=ジョブ型雇用という昨今の考え方に至ったのではないでしょうか。
また、日本では90年代末〜2000年代半ばに大企業を中心に、成果主義ブームが起こりました。しかし企業と社員側の間で信頼関係を築くことがむずかしくなり、ブームは続かなかったという経緯もあります。成果主義という言葉が流行らず失敗したから、今度はジョブ型という言葉にしようという意図的な側面もあるのです。
──人事評価の面でも、テレワークでできる仕事は限られている印象が強いわけですね。
以前はたしかにテレワークでできる仕事に制限は多かったです。しかし今は、基本的にテレワークでできる仕事に制約がなくなってきており、デスクトップ上で職場を再現できると考えています。
欧米のように、職務の内容や範囲が明確化された、職務限定型社員のような仕事の内容でないと、テレワークは難しいのでは、仕事ぶりが分からないから成果主義でないと難しいのでは、と考えてしまう向きもありますが、そもそも雇用制度や評価制度を変更するということが本質ではないのです。今あるテクノロジーをしっかり活用していけば、信頼関係の醸成やコミュニケーションの円滑化など仕事に必要な基本的なことはテレワークでもできるはずで、そこに向けて徹底的に努力していかないといけない。
ただし、日本の正社員は、職務や勤務地、労働時間などあらゆることが限定されておらず、辞令1本で異動させられてしまうなど、人事が非常に強力な力を持っています。多様で柔軟な働き方を目指すのであれば、今の制度は絶対に変えていく必要があります。働き方の自立性を自ら向上させていくには、在宅勤務やジョブ型雇用は親和性が高いため、一緒に推進していきやすい。
しかし、ジョブ型でないとテレワークができない、成果主義でないと評価できないというのはまったくの誤解。インフラが整備できていない、とことん使いこなしていないだけなのです。そんな先入観から抜け出すには、やはりテレワークを実際にやってみて、理解していかないと前には進みません。
テレワークに関連したコミュニケーション3つのハードル
──テレワークにおいても、デスクトップ上で職場を再現できるというお話がありましたが、逆にテレワークで再現しづらい部分もあるのでしょうか。
コミュニケーションに関してみると、3つほどハードルがあると考えています。
1つ目は、雑談のような事前に予定されていないコミュニケーションです。会議のような事前に予定されているコミュニケーションは、テレワークでも問題ありません。私が雑談として再現するのが難しいと考えているのは、オフィスですれ違ったときに生まれるような出会いがしらの雑談のこと。会議が終わった後にメンバーとちょっと立ち話をするような、オフィスでのインタラクションは非常に大切で、会話のなかから重要なヒントが得られることもあると考えています。しかし、このような事前に予定されていないコミュニケーションは、テレワークだと難しい。
2つ目のハードルは、社員同士の親近感・親密感をどう醸成するかという点です。フォーマルな仕事の信頼関係を醸成することはオンラインでもできますが、親密感とまではいかないでしょう。たとえば、厳しいと思っていた上司でも、対面で会ったり、飲食の席でいろいろ腹を割って話すことで、新たな側面が見えてくることで、仕事の向き合い方が大きく変わってくることもあるはずです。フォーマルな場から離れて潤滑油となるような場づくりは重要であり、オンラインではなかなかハードルが高いと考えています。
そして最もハードルが高い、3つ目のハードルとして挙げられるのが、新人が組織に馴染んでいくためのソーシャリゼーションです。特にメンバーシップ型雇用である日本の場合は、阿吽の呼吸が求められるため、より組織に馴染んでいく必要があります。新たに入る組織の文化はもちろん、働く建物にも企業との相性が感じられるものです。人事担当者も自分たちの仲間になってもらえるかどうか、新人の行動やたたずまいから判断していくこともあり、その環境に慣れていくプロセスは、オンラインだけでは難しい。
コミュニケーションの課題を乗り越える「分報」
──テレワークでは、コミュニケーションの課題がまだまだあるということですね。サイボウズでは、「分報」という仕事に関することやプライベートな話題など自由に書き込む、雑談の仕組みをオンライン上で行っているんです。

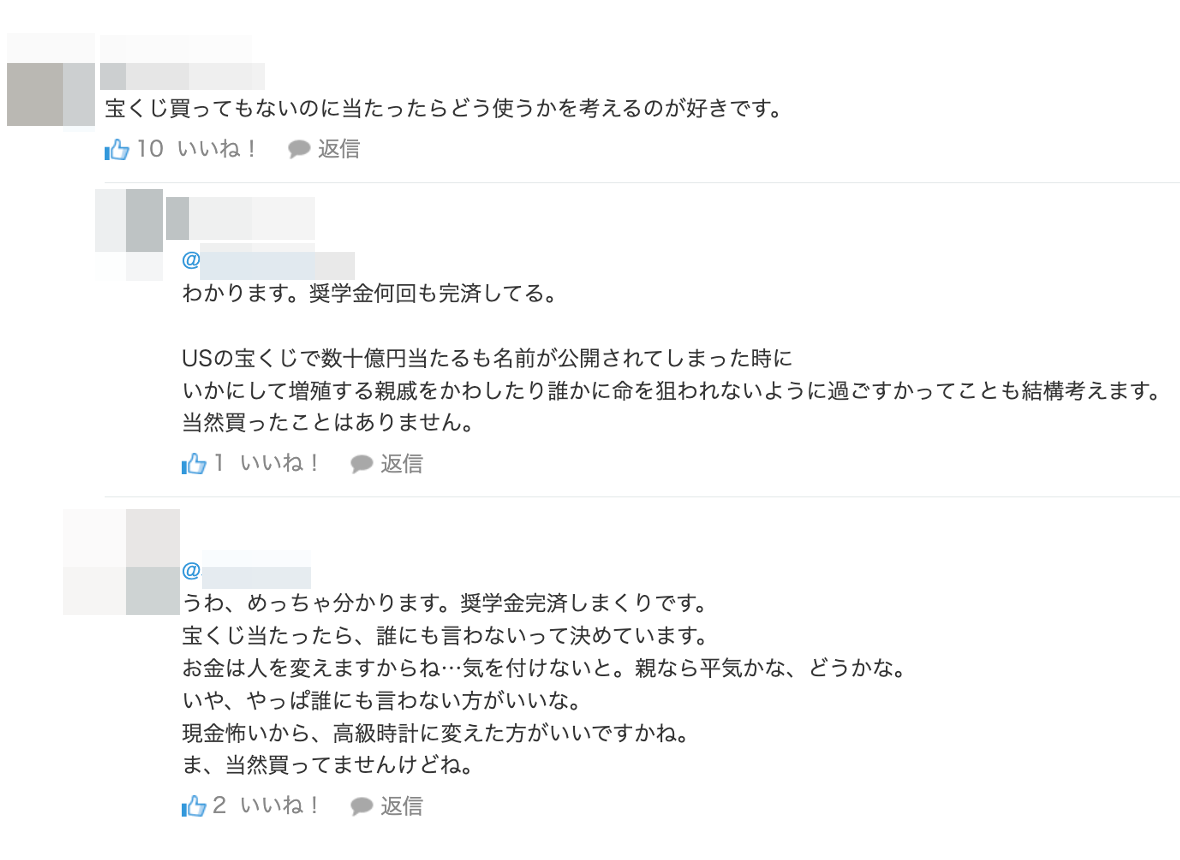
何気なくつぶやいたことを全然違う視点から共感してもらえるだけでなく、それが部門の垣根なく広がっているのがとてもおもしろいところですね。SNSがこれだけ広がっていることからもわかるように、人間はつぶやきを誰かに聞いて欲しいという思いがある。社会的動物である人間は、聞いてくれる人がいることで孤独感を解消することができるものです。
また、オフィスなら距離が離れていて聞こえないはずの人の声が自然に入ってくることも面白みの1つ。リアルのオフィス以上のコミュニケーションが可能になるわけですから。一般的な日本の企業は、違う部門の人たちの考えも知ってもらうために人事異動などがあり、それが幹部になるために重要な役割の1つになっています。ところが、分報のような仕組みで他部門の声が共有されていれば、そのようなシステムも必要なくなるかもしれませんね。そうすると、辞令1本で異動させられてしまうといった、これまでのメンバーシップ型のシステムのデメリットも解消されるのかもしれません。
ハイブリッドワークを、メリット・デメリットで考えるのは甘い。オンラインの可能性はまだまだある
──ここまで、テレワークの課題についてお伺いしてきましたが、テレワークを中心としながらもオフィスも活用し双方の良さを取り込む、ハイブリッドワークという新たな働き方について、その必要性を教えてください。
多様で柔軟な働き方を徹底的に推し進めていくためには、それぞれの働き方が許容できる仕組みが必要です。そうなれば、働き方は確実にハイブリッドになることでしょう。ただし、“オンラインも職場も双方メリット・デメリットがあるからハイブリッドワーク”というのは、すごく甘い考え方だと思っています。
なぜかと言えば、オンラインや仮想空間上で、どこまでできるか突き詰めていないから。徹底的にやったうえでハイブリッドとは何なのかを考えれば、オフィスの概念はまったく変わります。徹底して突き詰めていかないと、実はハイブリッドワークはうまくいかないのです。
──オンライン上でやりきったうえで、選択できる環境を用意するということですが、オンライン上でできること、オンラインの可能性はまだまだあるわけですね。
多様で柔軟な働き方の一環としてオフィスも選択できるようにしておくことはもちろん重要ですが、とことんオンラインでできることを確保したうえで、最後に働き手が選べることが重要です。また、その環境づくりで重要なのは、情報格差をどれだけなくすことができるかという点も忘れてはなりません。オフィスでも自宅でも同じ情報がオンライン上で共有できる仕組みをしっかり整備しておかなければ駄目です。オンライン上でやりきることができれば“どっちでも同じ”になる。そんな環境を作れてこそハイブリッドであり、だからこそどちらでも柔軟に選択できるわけです。
先ほどオンライン上で難しいコミュニケーションの1つとして、新人が組織に馴染んでいくためのソーシャリゼーションの話をしましたが、新人をあらゆる訪問先などにZoomを通じて参加させ、先輩のそばで話を聞かせるといった取り組みでうまく解消している例も耳にしています。
まさにこれはオンライン版の「かばん持ち」のようなものですよね。リアルではなかなかできないような数の会議への同席もできることでしょう。このように、リアルではできなかったことがオンラインであれば可能になることも多いのです。オンライン上でも、工夫次第でやれることはまだたくさんあるはずです。
分報などの仕組みはまさにそうです。以前は同じ職場にいても「同じ釜の飯を食う仲間」、つまり阿吽の呼吸も含めた一体感まで感じられるのは同じ部屋や部署にいるメンバーが中心でした。しかし、それがデジタルになって、以前よりも釜のサイズが大きくなり、1つの大きな釜の飯をみんなで食べることができるようになる。つまり、オンライン上のツールを使うことで、これまで以上に一体感を感じられる組織になれるわけです。

ハイブリッドワークが浸透するための鍵
──最後に、多様で柔軟な働き方を進めていきたい企業に向けてのメッセージと、ハイブリッドワークの今後の展望についてお聞かせください。
コロナ禍による働き方の変化は、特別なことを意味するわけではなく、1つのきっかけにすぎません。多様で柔軟な働き方、選択できることは以前から重要だったものの、徹底してこなかった。DX含めたデジタル化は、中途半端ではなく徹底してやることが欠かせません。
出社がだめということではなく、オフィスに来て働きたい意思も尊重しながら、それぞれが一番パフォーマンスを発揮できる場所を自由に選択でき、かつそこに情報格差が生まれてこないようなシステムや仕事の進め方に作り変えていく。
これからは、オンラインの徹底をうまくやることによって、働き手は働く場所を選択でき、企業にとっても生産性を高めることができます。つまり、ハイブリッドワークは従業員の双方がwin-winの関係になる取り組みなのです。コロナ禍に関係なく、ハイブリッドワークは進めていかなければならないと思っています。

